※ 本記事は過去のXの投稿を大幅に改稿したものです。またネタバレを多く含みます。ご注意ください。
この映画について書く「フロントライン」
先日劇場に何ヶ月かぶりに映画を観に行った。僕は分子生物学の方の畑の人間に突入しようとしているわけだから、中々に考えさせられた。ウイルスのあたりとかね。その中で「専門家」と「非専門家」、そして非常時にどういうふうな立ち振る舞いをすればいいのか、というあたりについて色々と考えさせられたで、つらつらと書いていきたいと思う。
あらすじ
日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」での実話を基に、未知のウイルスに最前線で立ち向かった医師や看護師たちの闘いをオリジナル脚本で描いたドラマ。
2020年2月3日、乗客乗員3711名を乗せた豪華客船が横浜港に入港した。香港で下船した乗客1名に新型コロナウイルスの感染が確認されており、船内では100人以上が症状を訴えていた。日本には大規模なウイルス対応を専門とする機関がなく、災害医療専門の医療ボランティア的組織「DMAT」が急きょ出動することに。彼らは治療法不明のウイルスを相手に自らの命を危険にさらしながらも、乗客全員を下船させるまであきらめずに闘い続ける。
(映画.com https://eiga.com/movie/103120/#google_vignette より引用)
この映画が描くのは「現実」か「虚構」か?
虚構の延長線上は現実か
このトピックは僕も演劇関係者なので、中々悩むことが多いトピックである。虚構は現実が作り出すだろうし、現実は虚構が作り出すだろう。具体的にいうならば、誰かと誰かの恋愛についての虚構作品を作り出すとき、劇作家の現実での経験をもとに形成するだろう(意識下であるかどうかという議論は置いておこう)。この作品はそこらへんについて考えさせられた。
というのも、普通の映画ならここで主人公の大切な人が倒れて御涙頂戴するだろうな、みたいなポイントを華麗にスキップしていく。確かにドラマチックにしたんだね、という部分は何十箇所もあるが、それでも普通の映画と比較したら少なかった(比較するなら「感染列島」とかが一番マッチするだろう)。この映画は実話を基にしたフィクションではないだろう。まさにノンフィクションと遜色のない作品であると感じた。
現実に引き込まれる瞬間
僕らは「コロナ・ネイティブ」世代だろう。あの地獄の世界を身をもって体験している。疑いようのない事実だ。僕と同世代の人間なら学校行事がなくなった、何ヶ月も学校は休みになった、夏休みはほとんどなかった、とかの経験があるのではなかろうか。
あの時代は、変な閉塞感があった。それは何かわからない粒子が僕らの空気に漂っている。そして吸ってはいけないと言われる。それがきっと「コロナ・ネイティブ」世代の共通言語になっているだろう。それが映画に現れてくる。共通言語があるから、映画と分かり合える。共通言語があるから、画面の先は現実になる。
ではその共通言語はどのように伝えてくるのか。それは劇中の報道番組そのものである。記者というキャラクターである。ちなみに後述するように記者に関しては、違う意味で本来は置いているのだろうと分析しているが、それでも「共通言語」を核として考えることもできると思われる。
官僚の「対立構造」
踊る大捜査線という傑作とも言える、ドラマ・映画の一連の作品がある。この作品における核となっているのは「官僚」と「現場」の対立構造ーしがらみである。ただ今回の作品は先述した通り「ノンフィクション」という名の演劇である。その対立構造もできるだけ最小限に抑えられているのは、観ていてストレスが非常に小さかった。
小栗旬が演じるDMATの責任者と松坂桃李が演じる厚生労働省の官僚、これが普通の作品であれば対立し続けるだろう。ただ「フロントライン」はあくまでノンフィクションであるから、あまり対立しないように形成されている。ここに普通の映画として観たらつまらないかもしれない、という感想を抱いた。ただここで対立するような作品にしていれば、僕は途中で帰っていたかもしれない。
ただ少し物足りなかったとするなら、官僚の地道な努力がほとんど描かれなかったことである。この部分だけは本当に残念だと思った。あんなにクールなはずがないと思う。僕が演劇に関わるときに考えていることはほぼ「リアリティ」であり、それがドラマチックと対立したとしても、僕は「リアリティ」をとると断言するほど、大事にしている。それはちょっと残念だったと感じた。
専門性と現実性
専門家という称号
専門家というのは、専門領域に関して高度な学識を持っている人のこと、となるだろう。その専門家の無意味性、使えない瞬間を何も隠さずにこの作品は描いている。「専門性」よりも「現実性」が非常時は重要視される。それを気づかないで、専門性を押し付けようとするならば、それは全く「専門家」ではなくなる。害悪である。
共通敵と誰かを倒そうとしないのがこの映画だった。理解させようとする。それが現実性であり、リアリティである。でも少なくともドラマチックではないだろう。ただそれがあの船の中の現実だと言われれば、疑いようがない。
森を見るためには
「木を見て森を見ず」という諺がある。この映画での専門家の描き方はまさにこの諺の通りであろう。でも非常時に森を見ることはできるのだろうか。少なくとも僕は無理だ。森を見ることの難しさをひしひしと感じる。
そのためには常に専門領域から離れたところで専門領域を見ていくことが大事なのではないだろうか。少なくとも僕にはそれしかまだ答えを持っていない。
「マスゴミ」として描いた作品の向こう側は
「マスゴミ」の登場
マスコミの堕落を「マスゴミ」というようになったのは果たしてどれだけ前のことだっただろうか。そこまで昔ではなかった気がする。でもその前からマスコミが取材をすることにあまりいい気分を抱いたことはそんなにないと思う。
それこそがマスコミのステレオタイプそのものであろう。これを表現したいがために、この映画の主要キャラクターにもマスコミを複数登場させているのではなかろうか。こちら側についてももう少し深く描いて欲しいと思うところはあるものの、それは別の作品に譲った方が良いのではないかと感じた(例えば「エルピス」とか)。ただどうしても物足りないと感じたのは僕だけだろうか。
「マスゴミ」として描いた作品の向こう側は
この作品もマスコミのステレオタイプを批判するタイプの映画であった。ただ1つ解せないことがある。この作品も引用やらなんやらでトラブったようだ。ほぼノンフィクションですよ、と言っているような映画で取材をそこまでやっていないこと、筆者の意図せぬ方向に文章が解されていること、これらについてはあまり評価できない。というか中途半端な感覚が否めない。どうせやるならいいことも悪いことも全部描けよと思った。
総じて…
いい映画だったとは感じた。ただこれはどの作品にも共通して言えることではあるが、作品の中で描かれていることが全てと考えてはいけない。と感じた。観てタメになる作品だとは思う。同時期を描いて、最近公開になった「この夏の星を見る」も気になっている。


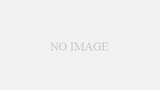
コメント